シリーズ安全保障第二回日本国憲法と安全保障
- 管理者
- 2015年9月29日
- 読了時間: 2分
安全保障とは、なんらかの方策により安全な状態を保つことである。世界において安全保障は、直接的にしろ間接的にしろなんらかの軍事力を用いているものがほとんどである。バチカン市国など武力を持たずに独立を保つ国家はあるが、ごくごく一部の例外である。 さて日本における安全保障はどうだろうか?サンフランシスコ講和条約以後アメリカとの安全保障条約、そして自衛隊という「必要最小限の実力」をもっていることから、軍事力を用いた安全保障体制といえる。しかしこの現実は、その1項で戦争を放棄し、2項で戦力を放棄している日本国憲法9条と大いに矛盾していることは明らかである。歴代政権はこれを憲法解釈によって、憲法との整合性を求め正当化してきたわけであるが、このままで良いのだろうか?安倍政権は再び解釈改憲を行い、安全保障法案を成立させ、さらに現実の憲法との乖離が進んでいる。 日本人は憲法を現実にあわせるべきなのだろうか?それとも現実を憲法に合わせるべきなのだろうか? ここで仮定してみよう。日本が憲法に現実に合わせ、日米安全保障条約を破棄し、駐留米軍を撤退させ、自衛隊も解体することを目指す。この場合において日本の安全保障はどのようになされるのであろうか?実際に1947年の日本国憲法施行から1951年のサンフランシスコ講和条約までは、占領下とはいえ仮定の状況に近いものがあった。1950年に出版された法学博士田岡良一氏の著書「永世中立と日本の安全保障」を読むと、憲法を遵守し、安全保障を行う唯一の方法は「永世中立」としている。氏の書くところの「永世中立」とは米ソによる保証の下行われ、どちらか一方と同盟を結ぶのではなく、平時は双方と友好関係を築き、一方から日本が侵略された場合には、もう一方と一時的な同盟に発展させ、撃退するというものだ。 確かに実現すれば良い考えかもしれない。しかし米ソ対立が表面化する50年代前半では夢物語であった。1955年ごろの米ソ雪どけの時期に全面講和できれば、オーストリアのように可能性があったかもしれないが、歴史のIFにすぎない。 結局のところ憲法に完全に合致する安全保障政策は、現段階では不可能だろう。自衛隊を憲法に明記することで、自衛隊を用いた安全保障の法的安定性を確保するべきだと私は考える。 ただ同時に武力に頼らない安全保障を模索することを止めるべきではない。 世界の例にとらわれず日本としての安全保障体制を気づいていくことこそが最も大切なのだ。



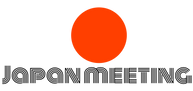
Comments